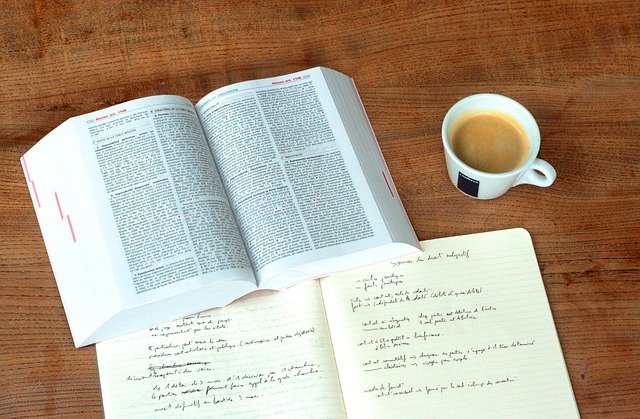同一労働同一賃金が施行されるのは、大企業の場合は2020年4月、中小企業の場合は翌年の2021年4月です。
この大企業、中小企業の区分は、厚生労働省によって区分けされていますが、業種によって条件がやや異なります。
ここでは、同一労働同一賃金施行における大企業と中小企業の区分けについてお話しましょう。
大企業と中小企業を分けるもの
同一労働同一賃金において、大企業と中小企業を分けるものは「資本金もしくは出資額」と「常時使用する労働者の数」です。
このどちらかが厚生労働省の定めた基準をオーバーしていれば大企業として扱われ、逆にオーバーしていなければ中小企業として扱われます。
また、常時使用する労働者の数には正規雇用者だけではなくパートやアルバイトも含まれます。
しかし、日雇いなどの臨時の場合は常時ではないので含まれません
業種ごとの違い
上記に加え、業種ごとによって条件が異なります。
業種は主に4種に区分されます。
・小売業
・サービス業
・卸売業
・製造・建設、運輸など上記に該当しない事業
この4種で同一労働同一賃金の条件は変化します。
例えば資本金・出資額の総額ですが、小売業とサービス業は、どちらかが5000万円以下の場合、卸売業は1億円以下、その他業種は3億円以下の場合、中小企業と判断されます。
また、人数ですが、こちらは小売業なら50人以下で、サービス・卸売業は100人以下、そしてその他業種は300人以下なら中小企業と判断されます。
このように、同一労働同一賃金は事業内容によって資本金の規模や人員に差があっても公平に中小企業、あるいは大企業の区分がされます。